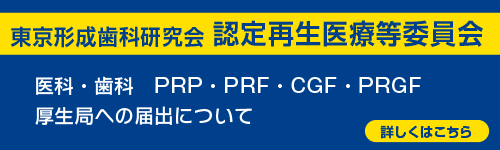【認定講習会および研修会】第2回 2021年5月23日開催
2023/11/09
2021年度 第2回 一般社団法人東京形成歯科研究会 主催 公益社団法人日本口腔インプラント学会 認定「講習会」オンライン(Zoom)+対面 参加者募集のご案内
本講習会は、“オンライン”(Zoom)形式 “対面”参加形式のハイブリッド型で開催することとなりました。
尚、コロナ感染予防対策として、対面式での参加者数を制限し、定数を超えた場合は受講生の参加を優先します。検温実施、消毒等の感染対策を行いますが、自己責任のもとご参加いただくこととします。
新型コロナウィルス感染予防のため、本講習会は ZOOM(インターネット・WEB 会議システム)( https://zoom.us/jp-jp/meetings.html )にてオンライン同時配信いたします。ZOOM での開催は、JSOI へ申請し承認を頂いております。
ご参加なされる先生は、カメラ付きの PC またはタブレット端末(例、iPad)をご用意願います。双方向で会話ができ、PPT等の発表スライドも十分に閲覧可能です。
Zoom への接続方法が不明な先生は、どうぞお気軽に当会事務局までご連絡下さい。先日配しました「Zoom アプリのダウンロード~ミーティングを始めるまでの手順」を再送します。※従来通り、本講習会開催の数日前に「Zoom“接続テスト”」を実施します。改めてご案内致します。
※その他、ご不明な点につきましては、どうぞお気軽に当会事務局までご連絡下さい。
講演
| 「デジタルデンティストリーの将来と可能性・最新インプラント治療ガイドライン」
※講演形式:“オンライン” ※「Zoom」配信 〇撮影・録画 禁止 |
|
 |
三軒茶屋マルオ歯科 丸尾 勝一郎 |
| 「ガイダンス 2021 年度 新潟大学×TPDS 共同研究 / 論文の読み方・まとめ方」
※講演形式:“オンライン” ※「Zoom」配信 〇撮影・録画 禁止 |
|
 |
新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野 准教授 川瀬 知之 |
| 「医療倫理と法律」
※講演形式:“オンライン” ※「Zoom」配信 〇撮影・録画 禁止 |
|
 |
弁護士 若松 陽子 |
開催概要
※開催概要は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承願います。
- 日時
- 2021年 5月 23日(日)
- タイムスケジュール
-
- 9:30~
- 挨拶 「月岡 庸之(東京形成歯科研究会会長)」 ※“オンライン”参加
講義 「講師:丸尾 勝一郎」 ○座長:辻野 哲弘(JSOI指導医)(試験対策委員会委員長)
※ “オンライン”講義 ※「Zoom」配信 - 12:30~
- 休憩(昼食)
- 13:00~
- 講義 「講師:川瀬 知之」
※ “オンライン”講義 ※「Zoom」配信 - 15:00~
- 休憩
- 15:05~
- 講義 「講師:若松 陽子」 ○座長:渡辺 泰典(JSOI指導医)(学術委員会委員長)
※ “オンライン”講義 ※「Zoom」配信 - 18:05~
- 終了(予定)
- 場 所/会 場 及び Zoom(インターネット・WEB会議システム)接続について
-
○対面参加形式の場合
オクデラメディカルインスティテュート セミナー室
※当日は、「4F・王子フィットネス&ジム」までお越しください。5Fセミナー室へは4Fを経由して頂きます。
住所:〒114-0002東京都北区王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ
TEL:03-3919-5111 / FAX:03-3919-5114 ※当日の連絡先(事務局) TEL:090-4913-8677○オンライン(Zoom)形式参加の場合
Zoom
Zoom(インターネット・WEB 会議システム)( https://zoom.us/jp-jp/meetings.html )での開催となります。
講習会当日、下記の内容よりご参加下さい。
ミーティング ID: ×××× ××××
パスワード: ×××× ××××
※部外者からの進入を排除するため、対外秘となっております。別途、事務局までお問合せ下さい。
1) Zoomアプリ ダウンロードをお済みでない方
添付「Zoomアプリのダウンロード~ミーティングを始めるまでの手順」の内容に沿って進めていただき、上記の「ID」「パスワード」を使用し、ミーティングに参加して下さい。
2) Zoomアプリ ダウンロードがお済みの方
添付「Zoomアプリのダウンロード~ミーティングを始めるまでの手順」内の“サインイン”からスタートし、上記の「ID」「パスワード」を使用し、ミーティングに参加して下さい。
※講習会当日、ミーティングに参加後、接続できないようであれば、当会事務局(℡ 03-3919-5111)までお電話をお願い致します。参加者の先生からのミーティングの参加を、こちら(事務局)で許可することで、ミーティングへの参加の接続が完了となります。
※開催前に「Zoom接続テスト」を実施します。別途、ご案内致します。
Zoomアプリのダウンロード ~ ミーティングを始めるまで の手順 - 受講料
- ○(一社)東京形成歯科研究会主催 JSOI 認定「 講習会 」受講生:無料
※2021 年度(一社)東京形成歯科研究会主催 JSOI 認定講習会 受講料に含まれる。
○(一社)東京形成歯科研究会会員:無料
※2021 年度(一社)東京形成歯科研究会「年会費」に含まれます。
○ 再生医療等提供機関 管理者:要相談(下記「お問合せ先」まで)
○ 一般参加者(受講希望者):25,000 円 ※対面参加形式の場合:昼食代(お弁当)含む - 振込先
- 銀行名:みずほ銀行
支店名:王子支店(店番号 557)
口座種類:普通預金
口座番号:1517592
口座名義:シヤ)トウキヨウケイセイシカケンキユウカイ 一般社団法人東京形成歯科研究会 代表理事 奥寺元
※「振込手数料」は参加者様にてご負担をお願い致します。※お振込の際に発行される「振込明細」を領収書と致します。 - 振込期日
- 2021年 5月 19日(水)
- 参加申込方法
- 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送り下さい。
FAX:03-3919-5114
E‐mail:okudera@carrot.ocn.ne.jp
- 参加申込締切日
- 2021 年 5月 18日(火)12:00 正午
- [お問合せ]
- 東京形成歯科研究会 事務局 担当:押田浩文
〒114‐0002
東京都北区王子2‐26‐2 ウェルネスオクデラビルズ3F オクデラメディカル内
TEL:03‐3919‐5111
FAX:03‐3919‐5114
E‐mail:okudera@carrot.ocn.ne.jp
講演内容
講義 「デジタルデンティストリーの将来と可能性・最新インプラント治療ガイドライン」
三軒茶屋マルオ歯科 丸尾 勝一郎
近年のデジタルの進歩は目覚ましく、歯科領域においても補綴装置製作のためのCAD/CAMシステムが導入されて以来、デジタルの恩恵を受ける分野は拡大の一途を辿っている。さらに、口腔内スキャナの導入によって、患者の不快感の軽減だけでなく、歯科医師や技工士も煩雑な作業が減り、大きな恩恵をもたらしている。さらに、CADソフトの簡易化、あるいはCAM機の小型化に伴い、個人歯科医院規模でもフルデジタル化が可能となってきた。インプラント治療においても、外科および補綴の両側面においてデジタルとの親和性が高く、現在ではフルデジタルによる治療の完結が可能となった。本講演では、デジタルの導入ならびに最新治療ガイドラインと共にできるだけわかりやすく解説していきたい。
丸尾 勝一郎 (Katsuichiro Maruo D.D.S., Ph.D.)
歯学博士・インプラント専門医(日本口腔インプラント学会)
【略 歴】
- 2005年
- 東京医科歯科大学歯学部卒業
- 2009年
- 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 インプラント・口腔再生医学分野修了(歯学博士)
- 2010年
- 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座 助教
- 2011年
- 同附属病院 インプラント外来医局長
- 2012年
- 米国ハーバード大学歯学部インプラント科 ITIスカラー・研究員
- 2013年
- 神奈川歯科大学大学院 口腔機能修復学講座 咀嚼機能制御補綴学分野 助教
- 2015年
- 同附属病院 診療科講師
- 2017年
- 日本口腔インプラント学会 専門医取得
同大学院 口腔統合医療学講座 補綴・インプラント学 講師 - 2018年
- 同大学院 口腔統合医療学講座 補綴・インプラント学 非常勤特任講師
三軒茶屋マルオ歯科開院 - 2019年
- ITI Fellow就任
- 2020年
- 医療法人社団プライムエレメント設立 理事長就任
- 2021年
- 神奈川歯科大学 補綴・インプラント学特任准教授
恵比寿マルオ歯科 審美・インプラントスタジオ開院
所属学会
日本口腔インプラント学会 専門医
日本補綴歯科学会 ガイドライン委員会委員
ITIフェロー・広報委員会委員
European Association of Osseointegration (EAO) Member
日本デジタル歯科学会
日本顎顔面インプラント学会
所属スタディグループ:
Interdisciplinary Team of Dentistry (ITD) 主宰
講義「ガイダンス 2021 年度 新潟大学×TPDS 共同研究 / 論文の読み方・まとめ方」
新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野 准教授 川瀬 知之
2015年度の夏からはじまった共同研究も,この4月から6年目に突入した.血小板濃縮材料(PRPやPRFなど)の本質に迫り,科学的エビデンスをもって,それらの歯科再生医療への応用を促進させるというのが立ち上げの動機だった.その間,国際誌に論文26報,国内外の学会で発表26回と着実に実績を挙げてきた.また,これまでの日本口腔インプラント学会指導医試験において,東京形成歯科研究会は5名の合格者を輩出したが,本活動も受験要件を満たすという点で多大な貢献があったものと自負している.
昨今のコロナ禍のため,ラボに集まってもらい実験の見学と体験を通して研究の一端を理解してもらうという企画が困難となった.しかし,それを逆手にとって,昨年度は,これまでできなかった研究の基本(リテラシー)である「統計学」や「論文の読み方」の学習に力点を置き,基本から学習してもらうことができた.
また,日頃の臨床活動から肩の凝らない形で症例報告をしてもらい,科学的な見地からの有意義なディスカッションのやり方も習得してもらうように工夫した.こちらはまだ軌道に乗せるところまでは至っていないかもしれないが,今後も改善を図って有意義なものとしたい.
研究テーマに関しては,昨年度から引き続き「インプラントの表面処理としてのPRPの有用性の追求」と新たに「血小板中のポリリン酸の研究」を中心にすえて,これまで以上に世界に向けた情報発信を継続していきたい.
目的のいかんにかかわらず,まじめに取り組んでいただける方ならいつでも歓迎です.まずは押田さん(TPDS事務局)までご相談ください.
後半は「学会発表のまとめ方と論文書き方」について解説する.例年,総花的話に終始して教育的効果が上がっていなかったという反省に立って,今回は思い切って「論文(抄録)のまとめ方」に焦点を絞ってお話しすることにした.その裏には,まとめ方のポイントを身につければ,自ずと読むこともできるようになるという思惑があるわけである.ともかく,参加の先生ひとり一人が,次の学会で自分の臨床上の疑問や成果をまとめて発表するくらいの気持ちになって,つまり当事者意識をもって,参加していただきたい.例題を含めた演習形式も取り入れたので,是非,ペンを動かして,体験してください.
ついでながら,7月の研修会では,「臨床研究をはじめる前に知っておくべきこと・準備すべきこと」と題して,法律的なこと,倫理的なことから研究テーマの予備学習に至るまでをお話しする予定である.単なる思い付きから,技術の安定も待たずになんとなくデータ収集(本実験)に移行するのは,無駄以外の何物でもない.まず,事前に準備する「研究計画書」(設計図のようなもの)の必要性とそのための予備実験や文献検索の役割について理解してもらいたい.
論文を指導する立場にある指導者が昔からよく言っていることに「イントロを書かせてみれば,だいたいのレベルがわかる」という言葉がある.逆を言うと,「イントロもまとめられない者に論文は書けない」ということである.そのイントロとは,まさに「研究計画書」を反映したものである.興味を持ったテーマに関して,現在に至るまでの研究状況を俯瞰して簡潔にまとめられるようにしておくことは,すなわち,研究のスタートラインに立つことを意味しているということを多少とも実感してもらえるような話になっていれば幸いである.
川瀬 知之 (かわせ ともゆき)
新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野 准教授
新潟大学病院輸血・再生・細胞治療センター 品質管理責任者
日本歯科大学新潟生命歯学部認定再生医療等委員会委員
日本再生医療学会認定医
Odontology: Associate Editor
International Journal of Molecular Science: Guest Editor of Special Issue “Blood-derived biomaterials”
BioMed: Editorial board
Medicine (Wolter-Kluwer): Editorial board
Biomedical Reports: Editorial board
【略歴】
1985年 3月 新潟大学歯学部歯学科卒業
1986年 9月 新潟大学大学院歯学研究科中退
1986年 10月~1992年9月 新潟大学歯学部助手
1991年 1月~1993年 5月 米国マイアミ大学医学部博士研究員
1992年 10月~1993年10月 新潟大学歯学部講師
1993 年11月~現在に至る 新潟大学歯学部助教授 (2002年4月より准教授に配置換え)
1997年 11月~1998 年 1月 米国カンザス大学医学部およびマイアミ大学医学部にて客員教授
講義「医療倫理と法律」
弁護士 若松 陽子
近時には、医療倫理と法律の遵守が、臨床においても研究においても求められています。インプラント治療においても、同様であることは多言を要しません。
とりわけ、医療を巡る倫理指針や法規が、新に制定されたり、改定がなされたりしています。最新のものを知っておく必要があります。
インフォームドコンセントはもとより、ネットを介在した広告問題、利益相反など、各項目につき、具体的な事例をもとに解説いたします。
また、インプラントに関するトラブル問題を題材に、予防と解決に必要な点をお話いたします。
さらに、インプラント治療に関わる紛争には、典型的な類型があるため、上顎、下顎、メンテナンス、混合診療、麻酔ショック、説明義務などにつき、裁判例をもとに説明いたします。民事事件にとどまらず、刑事事件や行政処分についても言及します。
これらを知り、後顧の憂いなくインプラント治療に取り組んで頂きたいと願っています。
若松 陽子 (わかまつ ようこ)
【略歴・所属】
1983年~現在 大阪弁護士会登録
2003年 大阪大学法学研究科博士課程修了・博士(法学)大阪大学
2004~2020年 関西大学教授(法務研究科)
2011年~現在 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 顧問弁護士
所属学会
日本医事法学会
日本生命倫理学会